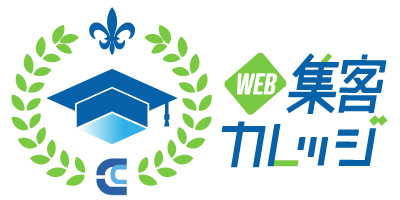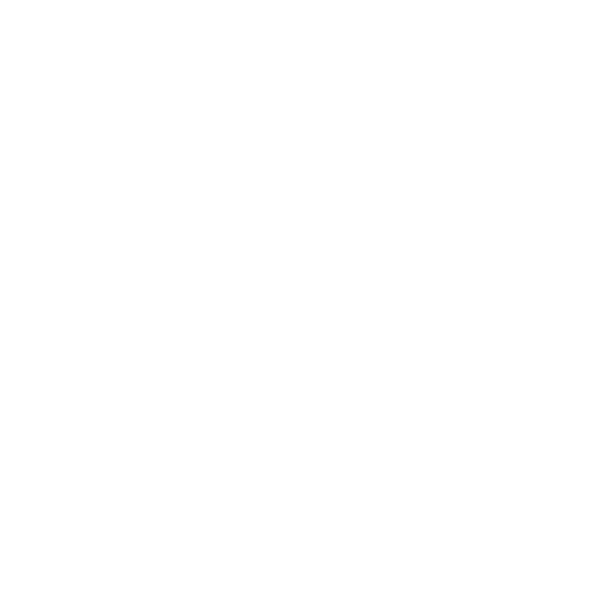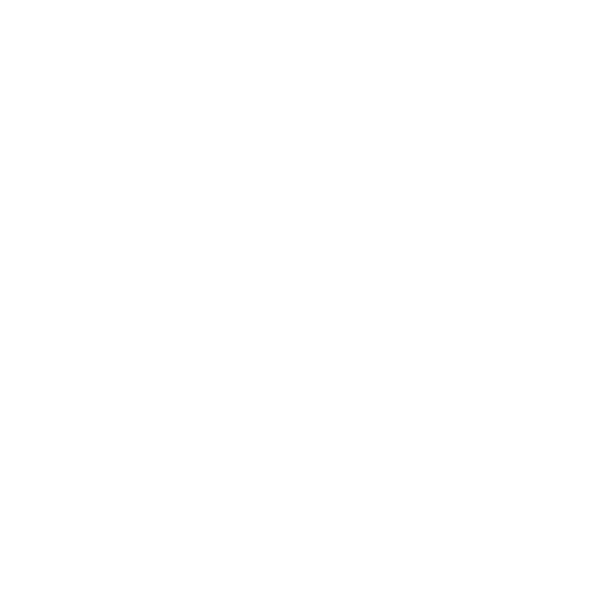インターネットが生活の一部となった今、どのような業種でも「ネット検索からの集客」が鍵を握っています。葬儀業界においてもそれは例外ではありません。かつては看板や口コミが主流だった葬儀社の集客も、今では「○○市 葬儀社」とスマートフォンで調べる時代です。
そんな中、注目されているのがGoogleマップを使った「MEO対策(Map Engine Optimization)」です。この記事では、MEOの基本から、葬儀社にとっての重要性、実践すべき具体的な対策方法、さらには専門業者への依頼の有効性まで、10,000字のボリュームで丁寧に解説します。Web施策に不慣れな方でも理解しやすく、今日から動ける実践知をお届けします。
MEOとは?

まずは「MEO対策とは何か?」を正しく理解することが、施策を成功に導くための第一歩です。SEOやローカルSEOといった似た用語と混同されやすい部分もあるため、それぞれの違いも含めて、丁寧に見ていきましょう。
MEO(Map Engine Optimization)とは、Googleマップ上で自社の情報を最適化し、地域ユーザーからの検索結果において上位に表示されるようにする施策のことです。たとえば「○○市 葬儀」「△△区 家族葬」などと検索した際、検索結果の上部に「Googleマップ+ビジネス情報」が表示されることがあります。この“地図情報”の上位に表示されるように工夫するのが、まさにMEO対策です。
これまではSEO(検索エンジン最適化)による上位表示が主流でしたが、現在はスマホでの検索が主流となり、「地図で探す」という行動が一般化したことで、MEOの重要性は一気に高まっています。特に、地域密着型である葬儀社にとっては、MEO対策を行うことで緊急性の高い見込み顧客にダイレクトにアプローチできるメリットがあります。
SEO対策との違い
SEOとは、検索結果の通常のWebページ一覧(いわゆる“青いリンク一覧”)で上位表示させるための施策です。一方で、MEOは「マップ+ビジネス情報(ローカルパック)」での表示に特化した施策です。表示される場所・仕組み・評価軸が異なります。
SEOが「全国規模でも競合が非常に多い」対策であるのに対し、MEOは地域・位置情報に基づいたローカル性の強い対策であるため、比較的上位表示が狙いやすく、コストも低く抑えられます。
さらに、SEOはコンテンツ制作や内部構造の最適化などテクニカルな要素が強く求められる一方、MEOは「Googleビジネスプロフィールの運用」「写真投稿」「口コミ対応」など、日常的な対応で効果を出すことが可能です。
ローカルSEOとの違い
ローカルSEOという言葉も混在しやすい概念です。ローカルSEOとは、地域に関連した検索結果で自社サイトや情報を上位に表示させるためのSEO施策全般を指します。つまり、MEOはこのローカルSEOの中に含まれる一つの施策です。
ローカルSEOには、自社サイトのSEO、地域ポータルサイトへの掲載、サードパーティのレビューサイト活用なども含まれますが、MEOはその中でも「Googleマップでの露出に特化した領域」です。
つまり、
- SEO:通常の検索順位対策
- ローカルSEO:地域に関する検索結果全体の対策
- MEO:Googleマップ上でのビジネス情報表示対策
という構造になっています。葬儀社においては、地域密着・即日対応が求められるため、まずは最優先でMEOから着手すべきだといえるでしょう。
葬儀社にMEO対策が重要な理由

葬儀社にとって、なぜMEO対策がこれほどまでに重要なのか?その根拠は、サービスの性質に密接に関係しています。以下の3つの理由を読み解くことで、MEO対策が“あらゆるWeb施策の中でも最優先で取り組むべき施策”であることが見えてきます。
地域密着型のサービスであるため
葬儀社の多くは地域に根差したサービスを提供しており、顧客もまた「できるだけ近くで、信頼できる葬儀社」を探す傾向にあります。実際、「○○市 葬儀」「△△区 家族葬」といった検索は日常的に行われており、このような地域ワードが含まれた検索結果で目立つ場所に表示されるか否かは、集客数を大きく左右します。
Googleマップの検索は、スマートフォンのGPS情報をもとに表示されるため、対策をしておくことで、**「今まさに困っている人」**の目に止まりやすくなります。地域での認知獲得、指名検索への誘導の前段階としても非常に有効です。
葬儀社は緊急性が高いため
葬儀というサービスは、事前準備をする人も増えている一方で、「突然」の状況で利用を決断しなければならない場面が依然として多く存在します。
そのため、「検索して、すぐに電話する」「まずは問い合わせてみる」という行動が非常に多く、検索結果の“1ページ目”の中でも特にマップ上の表示が最初にクリックされやすい傾向があります。
MEO対策は、そうした即決行動に直接つながる施策です。緊急度の高いニーズにおいては、「すぐ連絡できる」「すぐ場所がわかる」「口コミがある」=安心につながるため、MEOの表示がまさに「最初の選ばれるポイント」になるのです。
信頼性が重要であるため
葬儀は人生の節目に関わる非常にデリケートなサービスです。そのため、ユーザーは「どんな人が担当するのか」「費用は透明か」「トラブルは起きていないか」など、細かな点まで不安を抱えながら業者を選びます。
MEOでは、公式なプロフィール情報だけでなく、**第三者の声である“口コミ”や“写真の雰囲気”**が信頼の形成に大きな役割を果たします。SEOや広告では伝えきれない“空気感”や“誠実さ”がダイレクトに伝わることで、ユーザーとの心理的距離がぐっと近づきます。
葬儀社がMEO対策で得られるメリット

では、実際にMEO対策を行うと、どのような効果が得られるのでしょうか?ここでは、葬儀社がMEOを導入することで得られる4つの実践的なメリットについて、利用者の検索行動に即して詳しく解説します。
MEO対策にはデメリットも
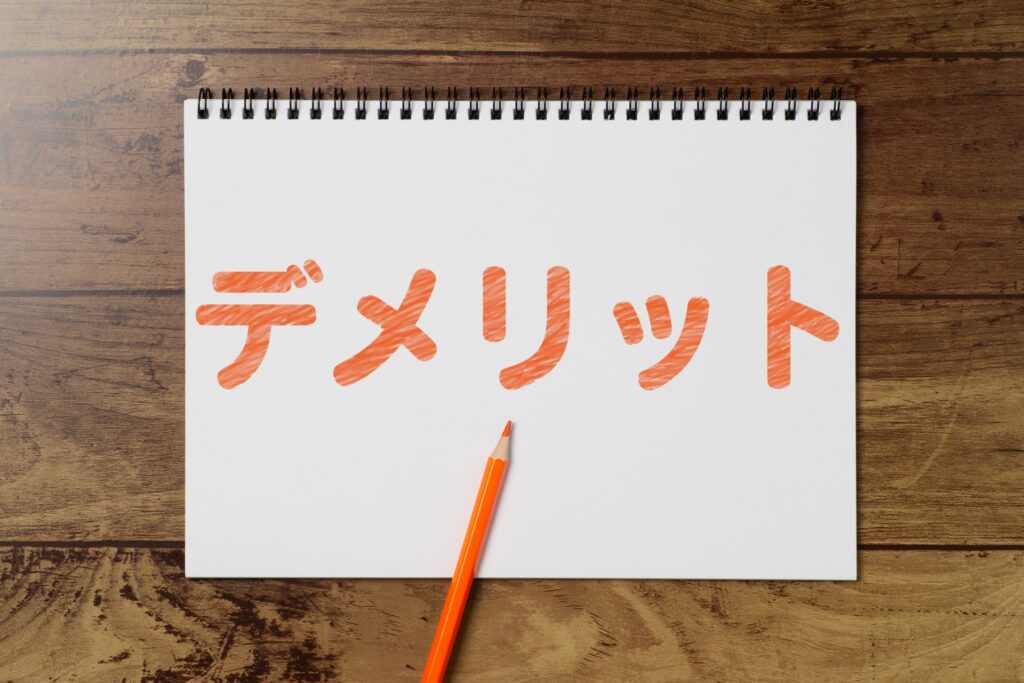
MEOは効果的な施策である一方、取り組む前に理解しておくべきリスクも存在します。特に、口コミという「第三者の声」が可視化される仕組みである以上、コントロールしきれない部分も出てきます。以下では、よくある2つの課題と、その対処方法について解説します。
ネガティブな口コミによるリスクもある
Googleの口コミ欄には、実際の利用者だけでなく、時に関係のない第三者からのコメントや感情的な批判が投稿されることもあります。これが新規顧客に対してマイナスの印象を与える可能性があるのは否定できません。
しかし、**ネガティブな口コミにこそ信頼を築くチャンスがあります。**丁寧な返信や真摯な対応が行われていれば、「この会社は誠実に向き合ってくれる」という評価につながります。口コミ返信は“見ている第三者”に対する接客だと捉えるとよいでしょう。
店舗数が多いと手間がかかる
複数会館を展開している葬儀社では、各拠点ごとにGoogleビジネスプロフィールを管理する必要があり、情報の更新・統一・対応に時間と労力がかかります。特に、営業時間や写真の追加、投稿の頻度を保つのが難しいと感じることもあるでしょう。
このような場合は、本社で一元管理する仕組みを整えたり、専門業者へ委託することで運用の負担を軽減できます。支店が多い企業こそ、早い段階で「MEO運用体制」を整えておくべきです。
葬儀社のMEO対策方法
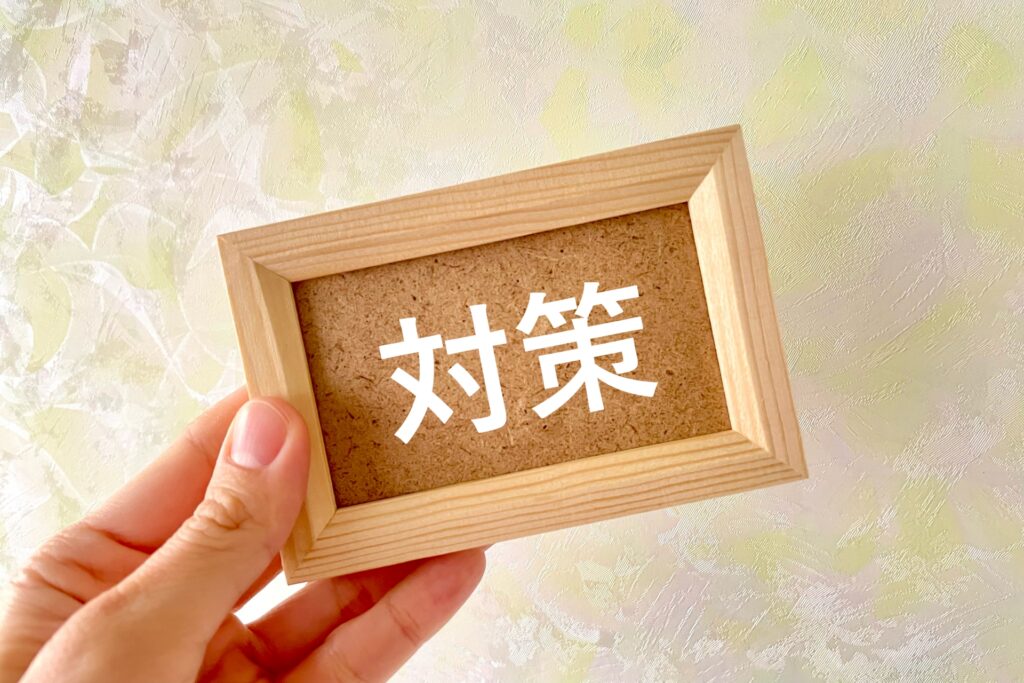
MEOの重要性が理解できたところで、次は「具体的にどうすれば良いのか?」という実践パートに移ります。ここでは、MEOにおける主要8項目について、初心者にもわかりやすく、具体的な設定例・ポイント・注意点を含めて丁寧に解説していきます。
① Googleビジネスプロフィールの登録
まずはGoogleビジネスプロフィールの公式サイトから登録を開始しましょう。
→ Google ビジネスプロフィール登録ページ
登録の際には以下の情報を正確に入力してください。
- 会社名(正式名称+支店名)
- 住所(郵便番号から正確に)
- 電話番号(代表・24時間受付かなど明記)
- 営業時間(年中無休や時間外対応なども記載)
- カテゴリ:葬儀場/葬儀社/葬儀サービスなどから最適なものを選択
申請後、Googleからの認証(ハガキや電話)が行われ、掲載が有効化されます。
② キーワードを設定し組み込む
検索されやすいキーワードを意識してプロフィール情報に組み込みましょう。
葬儀社で使われる代表的なキーワード:
- 「○○市 家族葬」
- 「△△区 火葬のみ」
- 「○○市 葬儀社 安い」
- 「○○区 葬儀 会館」
- 「○○斎場 直葬」など
説明文の中に自然な文章として含めるのがポイントです。例:「○○区の地域密着型葬儀社として、家族葬・火葬式に対応しています」
③ プロフィール情報の最適化
- 「説明文」には最大750文字まで入力可能。
→ 企業理念・対応エリア・相談受付内容などを丁寧に記載。 - サービスカテゴリ(火葬/家族葬/一日葬/一般葬など)を詳細に設定
- 特徴:「低価格プランあり」「24時間電話対応」「事前相談無料」など記載
④ 写真や動画などを掲載する
写真は「信頼性」と「雰囲気」を伝える大事な要素です。
おすすめの写真カテゴリ:
- 外観(昼・夜)
- 内装(祭壇・待合室・受付)
- スタッフの笑顔・対応中の写真(演出しすぎない自然体が◎)
- 実際の葬儀式場のセッティング例(無人/イメージ)
動画もあればベストです。会館紹介・アクセスガイド・サービス紹介など30秒〜1分程度が理想。
⑤ 投稿機能の活用
Google投稿機能を使うことで、最新の情報を定期的に表示できます。
投稿例:
- 「〇月の事前相談会予約受付中」
- 「家族葬専用ホール〇〇、内覧随時可能です」
- 「料金表の一部を更新しました」
- 「実際に寄せられた質問に回答中」など
「1週間に1度の投稿」を目安にすると、Googleからの評価も高まります。
⑥ 口コミの収集と管理
口コミ収集には工夫が必要です。
- 葬儀後に手紙やアンケートで丁寧に依頼
- 「ご満足いただけた方に、率直なお声をお願いしています」と案内
- 投稿されたら必ず返信を行うことが重要
→ 良い評価には感謝を、悪い評価には丁寧な説明とお詫びを
誠実な返信は、それ自体が「葬儀社の品格」を示す材料となります。
⑦ 公式サイトのSEO対策
MEOとSEOは連携しています。公式サイトに以下の対策を加えましょう。
- ページタイトルに「○○市の葬儀・家族葬なら△△葬儀社」など地域+業種を入れる
- meta descriptionを丁寧に
- 構造化データ(schema.org)を活用
- 問い合わせ導線を各ページに配置
⑧ 他サイトからのリンクを獲得する
- 地域ポータルサイト(例:○○商工会、△△市の○○情報)
- 提携寺院や終活業者からの紹介リンク
- 地元メディアでの紹介記事など
これらのリンクはGoogle評価を高め、MEOにも好影響を与えます。
MEO対策のポイント

対策を進める中で「何を守ればいいのか?」「どうすれば効果が出るのか?」を理解することが成果につながります。ここでは、MEO対策で特に押さえておきたい4つの視点をご紹介します。
MEOの仕組みを理解しておく
MEO順位の決定には以下の3要素があります:
- 関連性(Relevance):検索語句と情報の一致度
- 距離(Distance):検索者の現在地からの物理的距離
- 知名度(Prominence):口コミ数・Web露出・ブランド認知など
これらを満たすことで、上位表示の確率は大きく上がります。
情報は常に最新に保つ
臨時休業・スタッフ変更・新しい設備導入など、こまめに更新することで「生きているアカウント」としてGoogleからの評価も上がります。
最低でも月1回は更新チェックを行いましょう。
NAP情報は統一する
- Name(名称)
- Address(住所)
- Phone(電話番号)
これらの情報が、チラシ/自社HP/Google/SNS/外部ポータルで完全に一致していることがMEOでは非常に重要です。
Googleのガイドラインは守る
- 過剰なキーワード挿入
- 根拠のない虚偽情報
- 虚偽の口コミ操作(自作自演など)
これらは、アカウント凍結や表示停止の原因になります。常に正直で丁寧な運用を徹底しましょう。
MEO対策は専門業者に依頼するのもおすすめ

自社でMEO対策を行うのが難しい、あるいはよりスピーディに効果を出したい場合は、MEO特化の専門業者に運用を任せるという選択肢もあります。
対策の手間や人的コストがかからない
運用経験が少ない社内スタッフに任せると、運用ルールの理解からスタートし、継続が難しくなるケースも。外注ならプロが全ての工程を管理し、安定運用が可能です。
外注コストが低い
月額1万円〜3万円前後で運用可能なプランも多く、広告費に比べても安価。MEOは中長期施策であるため、初期費用+3ヶ月プランなどでスモールスタートしやすい点も魅力です。
自社で行うより早く成果が出やすい
Googleの仕様を熟知した専門家が、最適なアカウント設計・口コミ運用・競合分析を行うため、1ヶ月〜3ヶ月で成果が見えることも多く、業界でも高い効果が報告されています。
まとめ

葬儀社の集客手法として、MEO対策は「いま、最もコストパフォーマンスの良い施策」と言っても過言ではありません。地域性・緊急性・信頼性を重視するサービスだからこそ、Googleマップ上での見え方が“選ばれる決め手”になるのです。
MainCでは、葬儀業界に特化したMEO施策の知見とノウハウを多数持ち、運用から改善・レポートまでを一貫してサポートしています。
まずは無料相談からでも大歓迎です。
「現状の分析だけでもしてみたい」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
貴社の「地域で選ばれる葬儀社づくり」を、私たちが全力で支援いたします。